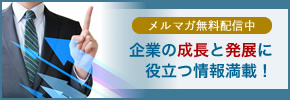認知症発症後でも家族信託を利用できるケースはあるか
近年、相続や老後の財産管理の手段として「家族信託」が注目されています。
信頼できる家族に財産の管理・運用を任せ、柔軟かつ円滑に資産を活用できる制度です。
ただし家族信託は契約によって成立するため、契約を結ぶ時点で本人に判断能力が求められます。
今回は、認知症発症後でも家族信託を利用できるケースはあるのかどうかを確認します。
家族信託とは
家族信託とは、財産を持つ本人が、信頼できる家族などに財産の管理や運用を任せ、その利益を別のひとが受け取る制度です。
法律上は「民事信託」と呼ばれ、主に高齢者の財産管理や相続対策に活用されています。
成年後見制度に比べ、財産の使い道や承継方法を契約で細かく定められるため、本人や家族の希望に沿った設計にできるのが大きな特徴です。
たとえば「自宅を子に管理してもらい、収益は配偶者が受け取る」といった形で活用できます。
認知症発症後でも利用できるケース
認知症と診断されても、軽度で判断能力が残っている場合には、家族信託を利用できる可能性があります。
医師による診断や周囲の状況確認により、契約内容を理解し、自分の意思で判断できる程度の能力があると認められれば信託契約の締結は可能です。
後のトラブルを避けるために、契約締結時に医師の診断書を添付するなど、判断能力があったことを客観的に証明できる形で手続きを行うとよいでしょう。
なお、認知症は、進行の早い病気でもあります。
軽度の認知症とされているタイミングであれば、なるべく早めに家族信託の利用を進めてください。
利用できないケース
一方で、認知症が進行し、契約内容を理解できない状態になっている場合には、家族信託を結ぶことはできません。
信託契約はあくまで本人の自由意思による契約行為であり、意思能力を欠いた状態では法的に有効とならないからです(民法第3条第2項)。
上記のようなケースでは、家族信託に代わる方法として、成年後見制度を利用するのが一般的です。
成年後見制度では、家庭裁判所に選任された後見人が財産管理や契約行為を代わりに行います。
まとめ
家族信託は、本人の判断能力が前提となる制度です。
認知症を発症した後でも、軽度で理解・判断が可能な場合には利用できるケースがありますが、重度になっている場合には利用できません。
家族信託を検討している場合は、元気なうちから準備を進めるのが重要です。
すでに認知症の兆候が見られる場合には、医師の診断を踏まえつつ、司法書士などの専門家に相談しながらスムーズに手続きを進めてください。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターが提供する基礎知識
-
生前贈与の効果的な活...
生前贈与は、子どもに現金を残しつつ、相続税がかかる財産をできるだけ減らすために行われます。一般的には贈与税の方 […]

-
成年後見制度とは?わ...
■成年後見制度とは成年後見制度は、判断能力が病気によって不十分になった方の財産を保護するための制度です。この制 […]

-
成年後見制度の種類と...
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。 ■法定後見制度法定後見制度には、本 […]

-
任意後見人ができるこ...
高齢化社会の進展に伴い、判断能力が低下したときの生活や財産管理に備える制度として「任意後見制度」が注目されてい […]

-
相続登記において委任...
相続によって不動産を取得した場合、名義を変更するためには相続登記が必要です。相続人自身が申請を行うこともできま […]

-
遺産整理
遺産整理は、亡くなった被相続人の遺した財産についての相続手続きを総称して言います。遺産整理ではまず、相続財産を […]

よく検索されるキーワード
お知らせ
法人概要
| 商号 | 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町105番地 ラテール旭2階 |
| 電話番号 | 045-489-4860 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 定休日 | 土日祝日(予約可) |
| 相談料 | 初回相談・見積無料(60分) |
| アクセス | 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分 |
| 関連サイト | 田近淳司法書士事務所ホームページ |