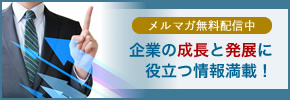相続登記において委任状が必要になるのはどんなケース?
相続によって不動産を取得した場合、名義を変更するためには相続登記が必要です。
相続人自身が申請を行うこともできますが、実務では司法書士や弁護士などに依頼して手続きを進めるケースが少なくありません。
その際に重要となるのが「委任状」です。
今回は、相続登記で委任状が必要になるケースを確認します。
委任状が必要となる主なケース
委任状が必要となる主なケースは、以下のとおりです。
- 専門家に手続きを依頼する場合
- 相続人の一部または全員が代理人に依頼する場合
- 特殊な事情がある場合
それぞれ確認していきましょう。
専門家に手続きを依頼する場合
相続登記の申請を司法書士などに任せる場合、本人に代わって手続きを行えるようにするために委任状が必要です。
注意すべきなのは、司法書士や弁護士以外の人が「業務」として代理申請を行うことは法律で禁止されているという点です。
司法書士法第73条・78条には、司法書士や弁護士以外の者が報酬を得て登記の代理を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があると定められています。
民間業者などが「代理で手続きを代行します」といったサービスを有償で行うのは、違法行為に該当するため注意してください。
相続人の一部または全員が代理人に依頼する場合
相続登記は、複数の相続人が共同で行うケースも多くあります。
遠方に住んでいる相続人や手続きに不慣れなひとがいる場合には、1人の相続人や専門家に代理を任せるのが一般的です。
この場合も委任状を作成しておくことで、円滑に手続きを進められます。
特殊な事情がある場合
たとえば高齢や病気で本人が役所や法務局に出向けない場合、代理人が申請を担う必要があります。
この場合にも、正式な代理権を示す委任状が求められます。
法定代理人の場合は委任状が不要
委任状が必要になるのは「本人の意思で代理人に手続きを任せる場合」です。
しかし、すべての代理人に委任状が必要というわけではありません。
未成年者や成年被後見人といった方が相続人となるケースでは、親権者や成年後見人が法律上の代理権を持っています。
上記のように、法律で当然に代理権が与えられているひとを「法定代理人」と呼びます。
法定代理人は、すでに法律によって代理権が認められているため、わざわざ委任状を作成する必要はありません。
まとめ
相続登記で委任状が必要となるのは、代理人に手続きを任せる場合が中心です。
相続人が全員揃って対応できる状況であれば不要ですが、実際には専門家や一部の相続人に任せるケースが多く、委任状の準備が欠かせません。
委任状は、形式や記載内容に誤りがあると無効になる可能性もあるため、事前に司法書士などの専門家に確認すると安心です。
一般社団法人すまいる相続・後見・信託センターが提供する基礎知識
-
成年後見制度 - 手...
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。そしてその申立の際には必要書類をそろえて […]

-
遺言執行者は相続人の...
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために重要な役割を果たします。しかし、相続人を遺言執行者に選任する場合には、 […]

-
相続できる人は誰?法...
相続する権利がある者を「相続人」といい、相続人になれると法律(民法)で定められている者を「法定相続人」といいま […]

-
認知症発症後でも家族...
近年、相続や老後の財産管理の手段として「家族信託」が注目されています。信頼できる家族に財産の管理・運用を任せ、 […]

-
遺産分割協議と遺産分...
遺言書がある場合、基本的にはその遺言書に従って遺産分割がなされますが、遺言書がない場合は誰がどの財産を相続する […]

-
相続放棄ができないケ...
相続放棄は、特定の条件を満たさないと認められない場合があります。この記事では、相続放棄ができないケースと対処法 […]

よく検索されるキーワード
お知らせ
法人概要
| 商号 | 一般社団法人すまいる相続・後見・信託センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒241-0024 神奈川県横浜市旭区本村町105番地 ラテール旭2階 |
| 電話番号 | 045-489-4860 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 定休日 | 土日祝日(予約可) |
| 相談料 | 初回相談・見積無料(60分) |
| アクセス | 【営業所】 相鉄線二俣川駅(北口改札)から徒歩4分 |
| 関連サイト | 田近淳司法書士事務所ホームページ |